さて、以前のブログでも問いかけましたが、もう一度、同じしつもんをします。
「あなたは、内向的な性格ですか。それとも外向的な性格ですか?」
いま一度、チェックしてみましょう。
以下のような特徴が3つ以上当てはまる人は、内向的な傾向が強いとして、「内向型」といえます。
• ゆっくり、慎重に行動するほう
• ひとつのことに集中するのが得意なほう
• 会話は人数の少ないことを好むほう
• ひとりの時間をしっかり取りたいほう
一方、以下のような特徴が3つ以上当てはまる人は、外向的な傾向が強いとして「外向型」といえます。
• 決断や行動が早いほう
• 同時に複数のことをこなせるほう
• 報酬や達成感を重んじるほう
• 仲間と一緒の時間が好きなほう
いかがでしたか。
いずれにせよ、人間には大きく分けて、内向型の人と外向型の人がいるのだということが、理解できると思います。
(最近の研究では、両方タイプを持ち合わせた「均衡型」の存在も明らかになっています)
そして、内向型の人にも、外向型の人にも、それぞれに、素晴らしい個性が備わっているといえます。
しかし、現代社会において、生きづらさを感じがちなのは、圧倒的に内向型の人の方であるといわれています。
なので、今回は(今回も、か?)、「内向型」に焦点を当てて、その個性に合った生き方・やり方などをお伝えしていきます。
(私自身が典型的な内向型ですので、内向型のことについて語れるからです)
まずは、前回の「内向型」のブログをご参照ください。
(※なお、当ブログ記事はnoteにも掲載しております)
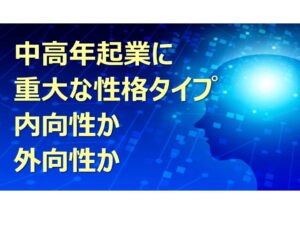
内向型と外向型を比較してみると・・・
では、この内向型の特徴について、外向型と比較しながら、その違いを見ていきます。
まず、内向型と外向型を比べたとき、その違いは、大きく3つあるといえます。
①.エネルギー補充の仕方の違い
②.外側からの刺激の受け止め方の違い
③.価値観を好むか、達成感を好むかの違い
では、これらの3つについて、ひとつずつ説明していきます。
①.エネルギーの補充の仕方
内向型と外向型の大きな違いの1つ目は、気力や体力などのエネルギー補充の仕方にあります。
内向型の人は、自分ひとりの時間を持つことで、気力や体力を補填する傾向にあります。
一方、外向型の人は、外で活動することによって、気力や体力を補填する傾向にあります。
例えば、内向型の人は、静かな場所で、ゆっくりと過ごすことで癒されて、心身が満たされます。
それに対して、外向型の人は、集団活動やイベントなどに参加することで気分転換になり、気力が満たされるのです。
私自身は、典型的な内向型ですので、人との接触が長く続いた後は、やはり疲れますし、ひとりの時間がほしくなります。
なので、会社員だった時は、拘束時間が長かったため、常に慢性的な疲労感を抱えていました。
②.外側からの刺激の受け止め方
2つ目の違いは、外側からの情報や体験に対する、受け止め方にあります。
内向型の人は、過剰な情報や体験を、受け取りたがらない傾向にあります。
一方、外向型の人は、むしろ、外からの情報や体験はウェルカムで、それを好む傾向にあります。
例えば、内向型の人は、自分の中で、課題や問題を反芻(はんすう)することによって、解決策を見つけるのが得意だったりします。
対して、外向型の人は、他者との会話や自身の行動から、問題解決の糸口を見つけるのが得意だったりします。
内向型の私は、やはり、外からの刺激や外側の変化が苦手でした。
会社員の時は、上司の何気ない一言が氣になって、夜眠れない、なんてこともよくありましたし、部署移動があった時などは、慣れるまで緊張感に包まれていました。
内向型の特徴である、「受け取った刺激を反芻する」ことは、「深く考える」という長所でもあれば、逆に、「考えすぎる」といった短所でもある、両面を持ち合わせていると思っています。
③.価値観を好むか、達成感を好むか
そして、3つ目の違いは、仕事や作業、行動などに対する、やり方や考え方にあります。
内向型の人は、仕事や作業をするときに、それが自分にとってどのような意味があるかを考えたり、自分の価値観と照らし合わせたりして、自分の内面を重んじる傾向にあります。
一方、外向型の人は、そこでの報酬や周りからの期待、目標達成の具合などを重んじる傾向にあります。
例えば、内向型の人は、仕事を与えられたときに、それは自分が得意なことか、不得意なことか、自分がする意味とは何か、などといったことを、内面と照らし合わせて、モチベーションが上下したりする傾向にあります。
対して、外向型の人は、評価の度合いや、達成度合いが、そのモチベーションの原動力となる傾向にあります。
内向型の私は、やはり、無意識のうちに、仕事にも“意味”を求めてしまっていたので、会社員時代は、辛い仕事も多かったです。
例えば、上司としては、部門として、その成果が見えやすい「システムの導入」を推進しようとして、部下へ指示を出していたことがありました。
しかし、私は、それより先に、理念の浸透であったり、チームワークの大切さであったりする、「教育や啓蒙」の推進の方が先だ、と考えてました。
まあ、システムチックに効率化を図ろうとしても、社員のマインドが変わらなければ、大した成果が出ないことは、分かっていましたから。
(なので、大した成果が出ないと分かっていることを、やらなきゃいけない、ということが、すごく辛かった…。)

内向型と外向型、真っ二つに分類できるわけではない
ここまで、内向型と外向型の違いを見てきました。
ただしながら、人間の性格タイプというのは、内向型と外向型の2つに、きっちりと分けられるほど、単純なものではありません。
(冒頭でも、両方タイプを持ち合わせた「均衡型」の存在も明らかになっている、とお伝えしました)
特に、近年の脳科学的な研究では、内向型と外向型において、次のようなこともわかっています。
「内向型と外向型では、脳内の神経伝達物質の受容体の構造レベルで違いがある」
つまり、内向型は、「脳内の神経伝達物質の受容体の構造が、非常に敏感になっているため、外からの刺激に対して高反応を起こしてしまう」、ということが分かっているのです。
また、心理学者のカール・ユングは、内向型と外向型について、それぞれ次のように定義していました。
内向型:「主観的な心的内容を通じて、人生に向き合う姿勢タイプ」
外向型:「外的な対象に、興味を集中させる姿勢タイプ」
そして、ユングは、次のようにもいっています。
「内向型と 外向型の違いというのは、あくまで傾向の違いである」
「あくまで傾向の違い」なので、両者の間は、きっちり線引きできるものではなく、グラデーションのようにつながっていると、考えられます。
しかし、グラデーションのようにつながっているにもかかわらず、社会における「生きやすさ・生きづらさ」という点においては、大きな違いが生じていると感じるのは、私を含め、数多くの人がいらっしゃると思います。
そうです。内向型というのは、この社会の中では生きづらさを感じやすい、といわざるを得ないのです。
(心理学者カール・ユング ↓)
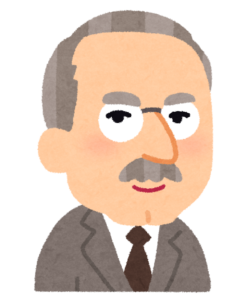
なぜ、内向型は生きづらくなりやすいのか
では、なぜ、内向型は、生きづらくなりやすいのでしょうか。
それは、現代社会には、外向型のほうに、有利な「文化・風習」があるためです。
例えば、縁の下の力持ちで寡黙な人よりも、リーダーシップを発揮する声の大きい人の方が、社会的に高い評価を受けやすい傾向がある、ということは、多くの人がうなずけると思います。
なので、現代社会は、いわば、外向型に向いている社会といえます。
そして、そんな外向型向きの社会においては、内向型の特徴が、いろいろと誤解されやすい状況にあります。
例えば、次のような誤解です。
(内向型の人は、)
・自信がなさそう
・無関心そう
・やる気が無さそう
・意固地である
・付き合いが悪い
(これらは、すべて、私がいわれてきたことです…💦💦
でも…、あとから思えば、いわれたこれらのことは、実際には、私自身が無意識のうちに、そう見えるようにしてしまっていたのかもしれません💦💦
そう、人から話しかけられないように…、頼まれごとをされないように…、そのようにして、自分自身を守っていたのかもしれません💦💦)
でも、一般的に、これらのことは、まったく誤解です。
内向型は、話に割り込むことが苦手だったり、控えめだったり、話の輪にうまく入れなかったり、物事の深い考察だったり、そのための決断や行動の遅れだったり、一人時間が大事だったり、する・・・。
単にそれだけなのです。
ここまで、内向型は生きづらさを抱えやすい、と綴ってきましたが、そうはいっても、世の中には、内向型と考えられている著名人もたくさんいます。
例えば、物理学者のアインシュタイン、元アメリカ大統領のバラク・オバマ、アップル創業者のスティーブ・ジョブズ、投資家のウォーレン・バフェットなどです。
また、日本人では、作家の村上春樹、音楽家の星野源、タレントのタモリ、大リーガーの大谷翔平選手などが、内向型といわれています。
なので、内向型であることが、必ずしも「不利」ではないのですね。
内向型は、外向型の現代社会においても、内向型の個性を活かせる環境を選択したり、活かせる術を身につけたりして、生きていけばよいのです。

内向型の個性を活かして生きるためのポイント3つ
では、外向型向きの現代社会において、内向型の人がその個性を活かして、さらに、生きやすくなるためのポイントを3つ、お伝えいたします。
ポイント1.心身のペースを保つ
ポイント2.優先順位を決める
ポイント3.得手・不得手の両方とも認める
一つずつ見ていきます。
1つ目のポイントは、心身のペースを保つことです。
外向型向きの現代社会で生きる内向型の人は、心身ともに疲れてやすいというだけでなく、その疲労回復にも時間がかかりがちです。
なので、自分自身がベストなコンディションを保てるペースをしっかり理解し、そのペースをなるべく崩さないように過ごすことが重要です。
そのためには、自分の生活リズムをきちんと把握することが大切です。
それには、次のようなことを理解しておきます。
・睡眠時間は何時間が最も適しているのか
・集中力が高まるのは1日のうちのどの時間帯か
・疲れが出やすいのは1日のうちのどの時間帯か
そして、ここからが大事なのですが、こうしたリズムに合わせて、予定を立てていくのです。
つまり、予定に自分を合わせるのではなく、出来る限り、自分のリズムに予定を合わせることを心がけてください。
特に、中高年の起業家は、相手の都合に合わせがちですが、出来る限り、まず先にこちらから、いくつかの都合の良い日、時間帯を提示させてもらうようにするといいでしょう。
例えば、私でしたら、睡眠は8時間取るのが、一番調子いいと分かっているので、出来る限り、22:30~06:30の睡眠時間帯を崩さないようにしています。
そして、日が暮れると疲れが出てきますので、夜の時間帯は、仕事や作業をしないようにしています。
なので、打ち合わせなども、出来る限り、日中の時間帯で提示させてもらっています。
2つ目のポイントは、優先順位を決めることです。
内向型の人が、よく頭を悩ませることとして、社交的な集まりに参加するかしないか、があるかと思います。
その場合には、判断基準として、次のしつもんで自問自考してみるといいでしょう。
「この会合は自分にとって意味があるのか?」
そこで、「意味」があると感じられれば、それは自分の価値観とあっているのですから、参加すればいいですし、「意味」がないと感じるなら、「先約がある」といって、断ればいいでしょう。
とはいえ、どうしても断れない付き合いもあるかと思います。
その場合には、気力や体力を消耗しすぎないよう、無理のない範囲を意識したり、翌日のスケジュールは余裕をもたせたりするなど、工夫してみてください。
例えば、私自身は、会社員時代には(特に中高年となってからは)、意味の感じられない(多くの)飲み会には、参加しませんでした。
また、たまに、同僚の歓送迎会などに参加しても、二次会には参加せずに、帰宅するようにしていました。
3つ目のポイントは、得手・不得手の両方とも認めることです。
内向型の人は、外向型向きの社会において、自分のできないことばかりに、目を向けてしまうことも多いかと思います。
しかし、自分の苦手なことは、苦手なんだ、とちゃんと自ら認めてあげることが大切です。
例えば、次のようなことです。
・友人をたくさん作れない
・作業に時間がかかってしまう
・会議ですぐに発言できない
・賑やかな場所は苦手
それでも、自分は、そういう個性を持った人間なのだと、素直に認めてあげましょう。
元来、この世のものは、すべて「陰と陽」の部分を持っています。
なので、先の苦手の例を「陰」ととらえるならば、それはまた、「陽」としてとらえ直すことができるということです。
例えば、次のように。
・友達少なくても、その分、深い友情関係が築ける
・時間はかかっても、集中して細かい作業ができる
・じっくり考えるので、的を得たことが言える
・1人、2人なら、人の話よく聞いてあげられる
自分が「陰」の部分と感じていることは、それを「陽」としてとらえ直して、得手・不得手の両方とも認めてあげられる自分になりましょう。
そもそも、「完璧な人間」なんて、この世に存在しないのです。
アルフレッド・アドラーも、次のようにいっています。
「不完全なありのままの自分を受け容れること、つまり、“不完全である勇気”を持つのだ」

主宰している、当プログラムは、内向的な人に向いています
現在、主宰している当講座プログラム、『売れる「個性と経験」で幸せ起業プログラム』は、内向タイプの人に向いてます。
理由としては、次のようなことがあげられます。
・1to1の個人講座である(←集合形式、集団行動が苦手の人でも大丈夫)
・最大1000日伴走します(←マイペースでゆっくりタイプでも大丈夫)
・あなたの「個性と経験」を大切にします(←「共感」「好き」を大切にした講座です)
・内向であるがゆえ、「うまくいかなかったストーリー」を大切にします(←当塾のコンセプト「中高年版ヒーローズジャーニー」です)
・講師(松崎)が内向タイプである(←同じタイプなので分かり合えます)
氣になったら、コチラの紹介ページをのぞいてみてください。

